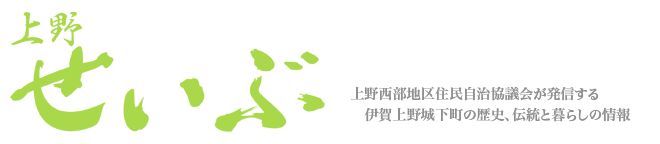No.12:テラコッタが見える街角(てらこったがみえるまちかど)

上野西部地区には外壁用陶磁器「テラコッタ」で飾られた建物が幾つか残されています。
テラコッタは焼き物の中で建築用・装飾用、または彫刻等の製品を指し、その歴史は古く「縄文土偶」や「埴輪」、中国漢時代から唐代の「俑(よう)」、西洋では古代ギリシャの「女神像」に起源を見ることが出来ます。
近代の伊賀地方では、大正末から戦前の昭和にかけて当時輸入に頼っていたものを全国に先駆けて開発・生産し、各地へ出荷されていました。
京都大学講堂を皮切りに東京・大阪・福岡等の高層建築に用いられ、我が国では正に草分け的存在として注目されていました。ところがその後産地拡散による低価格化、また新素材の出現と軍事体制下による需要の激減の為、まもなくその役目を終え姿を消してゆきました。
近代建築の一要素としての地位を確立しつつも、時の流れに翻弄されたテコラッタ。いまではかっての隆盛を懐かしむように静かな佇まいを見せていますが、当時の開発者の高い技術や意気込みも垣間見れ、その輝きは時代の先駆者としての気品と風格に満ち溢れています。これからも後世に残したい物のひとつとして大切にしてゆきたいものです。一ちょっと振り返ってみませんか?
参考資料 「窯業辞典」丸善株式会社
「世界大百科事典」平凡社 「田中善助伝記」前田教育会